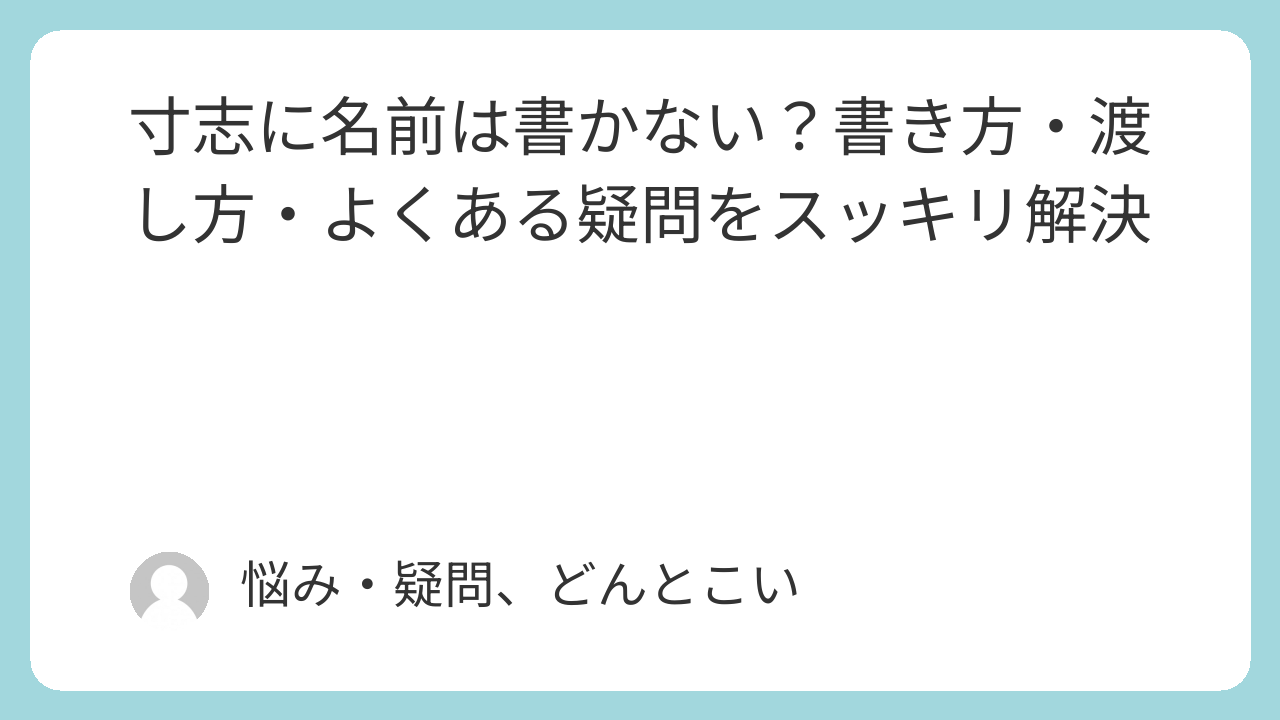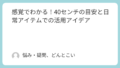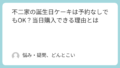「寸志を渡すとき、名前って書くの?」
「封筒の表書きは“寸志”でいいの?」
ちょっとしたお礼や感謝の気持ちを伝えるときに使われる“寸志”ですが、いざ準備となると迷うことも多いですよね。

この記事では、寸志の正しい書き方からマナー、タイミングまで、よくある疑問をまとめてスッキリ解決!忙しい毎日でも、スマートに気持ちを届けられるように、分かりやすくご紹介します。
寸志の基本知識
寸志の意味と目的
「寸志(すんし)」とは、文字通り「ほんの気持ち程度の贈り物」という意味があります。
金額は少額であることが一般的ですが、相手に対する感謝や労いの気持ちを形にして伝えるものです。
主に仕事や行事の場面で、感謝の意を込めて渡されることが多く、形式張った贈答とは少し異なるカジュアルな心づけとも言えます。
贈り物としての寸志
寸志は、現金を封筒に入れて渡すのが一般的な形です。
現金以外の品物を贈ることもありますが、「寸志」という言葉を使うのは主に金銭の場合です。
例えば、歓送迎会の幹事へのお礼や、イベントでお世話になった人への心ばかりの感謝の気持ちとして渡されます。

あくまで「気持ち」の表れなので、高額すぎると相手に気を遣わせてしまう可能性があるため注意が必要です。
寸志を送るタイミング
寸志を渡すタイミングは、その場面によって異なります。
歓送迎会や送別会であれば、会の始まりや最後のあいさつの前後にさりげなく渡すのが自然です。
結婚式や法事などフォーマルな場では受付時や着席前など、流れを妨げないタイミングを選ぶのがマナー。
タイミングによっては言葉も添えると、より丁寧な印象になります。
寸志と厚志の違い
「寸志」と似た言葉に「厚志(こうし)」があります。どちらも感謝の気持ちを表す贈り物ですが、意味合いと使い方に違いがあります。
寸志は自分が目下の立場として相手に対して「わずかですが」という謙虚な気持ちを伝える際に使われます。
一方、厚志は目上の人や第三者が、自分に対して贈ってくれた立派な贈り物に対して感謝を述べる際に用いる言葉です。
寸志の書き方
封筒の選び方
寸志を包む際の封筒は、白無地でシンプルなものを選ぶのが基本です。
水引が印刷されているタイプで問題ありませんが、派手すぎるデザインやキャラクター入りなどは避けましょう。

のし袋は、紅白の蝶結びが描かれているものが一般的です。
金額が少額であることが多いため、あまり仰々しい封筒だとバランスが悪く感じられることがあります。
表書きのルール
封筒の表書きには「寸志」と縦書きで書くのが基本です。筆や筆ペンを使って丁寧に書くと、より気持ちが伝わります。
ボールペンなどはカジュアルすぎる印象になってしまうため、避けた方が無難です。
なお、「御礼」や「謝礼」など、用途に応じて表書きが変わることもありますが、一般的な寸志の場合は「寸志」と記載しておけば問題ありません。
名前の記入方法
寸志を渡す際、封筒の下段中央にフルネームで名前を書くのが基本です。
ただし、職場やイベントで複数人からの寸志として渡す場合は、代表者の名前だけを書くか、「○○一同」としてまとめることもあります。

なお、あえて名前を書かないケースもありますが、礼儀として名前を記載する方が印象が良く、誤解を防ぐことにもつながります。
金額の記載について
寸志の封筒には、金額を表に書く必要はありません。
ただし、中袋がある場合はその中袋に金額を記載するのが一般的です。
金額は旧字体(壱・弐・参など)を用いて書くとより丁寧です。金額の書き方は「金○○圓也」などと記載し、「也」は省略しても構いません。金額を書く際は、桁数を間違えないよう注意しましょう。
中袋の使い方
中袋は、寸志の現金を直接包む内側の封筒のことです。
ある場合は使用し、ない場合は丁寧に紙で包むなど工夫をしましょう。
中袋には表に金額、裏に氏名や住所を書くのが基本とされています。中袋の記載も丁寧に行うことで、全体としてきちんとした印象を与えることができます。
寸志のマナー
目上の人への寸志の注意点
寸志はもともと「目下から目上へ渡す心ばかりの贈り物」という意味合いがあるため、目上の人に使うのが自然です。
ただし、表現やタイミングには注意が必要です。
例えば「ささやかですが」といった謙虚な気持ちを添えつつ渡すと好印象です。
また、金額が高すぎると相手に気を遣わせてしまう可能性があるため、相場を踏まえた額を選ぶようにしましょう。
送別会での寸志のマナー
送別会で寸志を渡す場合は、退職する人への感謝の気持ちを込めて準備します。
封筒は紅白の蝶結びが印刷されたものが一般的で、「寸志」または「御礼」と書くことが多いです。
手渡すタイミングは会の終盤や挨拶のあとなど、場の雰囲気を見て選ぶのがポイント。メッセージカードを添えると、より心が伝わります。
結婚式での寸志のマナー
結婚式で寸志を贈る場合、式を手伝ってくれたスタッフや受付をお願いした友人などに対して、「ありがとう」の気持ちとして渡すのが一般的です。
この場合の表書きは「御礼」や「心付け」とすることもあります。

あくまで感謝の気持ちを伝えるものなので、渡すときには一言添えるのを忘れずに。目立たないようにそっと手渡すのが大人のマナーです。
歓送迎会の寸志に適した表現
歓送迎会での寸志には、「感謝の気持ちを込めて」「これまでのお礼に」など、やわらかく伝える表現が適しています。
表書きは「寸志」でも問題ありませんが、状況によっては「御礼」や「謝礼」の方が合う場合も。
職場や団体でまとめて渡す際は「○○一同」と記載しておくと、受け取る側にも伝わりやすく、丁寧な印象になります。
寸志の見本と例文
表書きの見本
寸志の表書きは、封筒の中央上部に縦書きで「寸志」と書くのが基本です。筆や筆ペンを使用し、丁寧な文字で書きましょう。
こちらが表書きの例です。
:::*:::*:::*:::*:::*:::*:::*:::*:::
寸志
(中央上部に縦書き)
○○(自分の名前:中央下部に縦書き)
:::*:::*:::*:::*:::*:::*:::*:::*:::
会社や団体として渡す場合は、名前の代わりに「○○一同」と書くと良いでしょう。
裏書きの見本
裏書きは、中袋がない場合や、受け取る側にわかりやすくするために使用します。封筒の裏側左下に、自分の名前や住所を小さめに書くと丁寧な印象になります。
こちらは裏書きの一例です。
:::*:::*:::*:::*:::*:::*:::*:::*:::
〒123-4567
東京都〇〇区〇〇町1-2-3
佐藤 花子
:::*:::*:::*:::*:::*:::*:::*:::*:::
中袋がある場合は、裏書きを省略しても問題ありません。
具体的な寸志の例文
寸志を渡すときには、一言添えることでより心が伝わります。
こちらは実際に使える例文です。
* 歓送迎会で
「ささやかですが、これまでのお礼の気持ちです。どうぞお納めください。」
* 結婚式で
「本日は受付を引き受けていただき、ありがとうございます。ほんの気持ちですが。」
* イベントで
「お世話になりました。感謝の気持ちとして、受け取っていただけると嬉しいです。」
形式にとらわれすぎず、相手に敬意と感謝が伝わる言葉を選ぶのがポイントです。
寸志に関するよくある疑問
寸志に名前は書かないの?
寸志の封筒には基本的に名前を書きます。
特に個人で渡す場合は、表書きの下部にフルネームを縦書きするのが丁寧なマナーです。
ただし、匿名性を保ちたい場合や、団体で渡す場合には「○○一同」などとすることで対応できます。

まれに「名前を書かない方がスマート」と思われることもありますが、誤解を避けるためにも記名した方が安心です。
寸志の相場はいくら?
寸志の金額は状況や相手との関係によって異なりますが、一般的には1,000円~5,000円程度が多いです。
歓送迎会やお世話になった人への感謝であれば3,000円前後、結婚式での受付などをお願いした場合は5,000円程度が目安になります。
高すぎると相手が恐縮してしまうため、「あくまで気持ち」というバランスを意識するのがポイントです。
寸志にのしは必要?
寸志に「のし」は基本的に必要です。
コンビニや文具店で購入できるのし袋を使い、「紅白の蝶結び」が印刷されたものを選びましょう。
ただし、のし紙が別でついているタイプの場合、自分でのしを巻く必要があるため、ズレや曲がりに注意しましょう。
より簡単に済ませたい場合は、水引やのしが印刷されたタイプの封筒でも問題ありません。
寸志の表現に使える言葉
寸志を渡す際に添える一言には、感謝や丁寧さが伝わる表現が好まれます。
以下のような言い回しがよく使われます。
* 「ほんの気持ちですが」
* 「ささやかではありますが」
* 「心ばかりの品ですが」
* 「感謝の気持ちとして」
こうした表現を添えることで、相手に押し付けがましくならず、好印象を与えることができます。
特別な場面での寸志
仕事関係での寸志
仕事関係での寸志は、ビジネスマナーの一環として感謝の気持ちを伝えるために用いられます。
例えば、プロジェクトが一区切りしたときや、取引先へのお礼などで活用されることがあります。
ただし、金銭を直接渡すことが不適切とされるケースもあるため、企業のルールや相手との関係性を事前に確認することが大切です。
状況によっては現金の代わりに菓子折りなどを選ぶのも良い方法です。
お世話になった人への寸志
何かとお世話になった人に寸志を渡すのは、感謝の気持ちを伝えるスマートな手段です。
たとえば、引越しを手伝ってくれた友人や、地域のイベントでサポートしてくれた方などがその対象になります。
この場合、封筒はシンプルなものを選び、「御礼」や「心付け」と表書きしても問題ありません。
渡すときは「お世話になりました。感謝の気持ちです」と一言添えると丁寧な印象になります。
イベントでの寸志の考え方
イベント関係では、裏方で支えてくれた人や、主催に関わったメンバーへの感謝の印として寸志を渡すことがあります。

たとえば、文化祭や発表会、地域のお祭りなどで、目立たないところで働いてくれた人たちに「ありがとう」の気持ちを形にする場面です。
この場合も、金額はあくまで「気持ち程度」にとどめるのがポイント。封筒の表書きは「感謝」や「寸志」が適しています。
寸志の準備と記入の注意点
寸志を贈る準備リスト
寸志を用意する前に、以下のポイントをチェックしておくと安心です。
* 渡す相手とタイミングを確認する
* 適切な封筒(のし袋)を用意する
* 中袋が必要かどうかを確認する
* 筆ペンや万年筆など、記入用の筆記具を準備する
* 金額の目安を決め、用意しておく(新札が望ましい)
* 表書きや名前の記載内容をメモしておく
これらを事前に準備しておくことで、当日に焦らずスマートに対応できます。
記入をミスしないためのポイント
封筒や中袋に記入するときは、以下の点に注意しましょう。
* 表書きは縦書きで「寸志」と記載(筆ペン推奨)
* 名前はフルネームで、表の下部中央に記入
* 中袋には金額(旧字体が望ましい)と名前・住所を記入
* 間違えた場合は修正せず、新しい封筒に書き直す
* 書く前に薄く鉛筆で下書きするのも◎
丁寧に書くことで、相手への印象も大きく変わります。
寸志を渡す際の挨拶例
寸志を渡すときは、一言添えると気持ちがしっかり伝わります。
こちらはシーン別の挨拶例です。
ビジネスシーン
「ささやかですが、これまでのお礼の気持ちです。どうぞお納めください。」
結婚式の受付担当者へ
「本日はお手伝いいただきありがとうございます。ほんの気持ちですが。」
イベントスタッフへ
「陰ながら支えていただき、ありがとうございました。感謝の気持ちです。」
どの場合でも、笑顔と感謝の気持ちを忘れずに伝えることが大切です。
まとめ
* 寸志は「気持ちを形にした贈り物」で、主に目上の人に使う表現
* 封筒は白無地や紅白の蝶結びが印刷されたものを選ぶのが一般的
* 表書きには「寸志」と縦書きし、名前は基本的に記載するのがマナー
* 金額は1,000?5,000円が目安で、相手に気を遣わせない金額に
* 渡すタイミングや言葉が丁寧だと、より気持ちが伝わりやすい

ほんの少しの心遣いが、相手の記憶に残ることもあります。形式にとらわれすぎず、「ありがとう」の気持ちを大切にしていきたいですね。