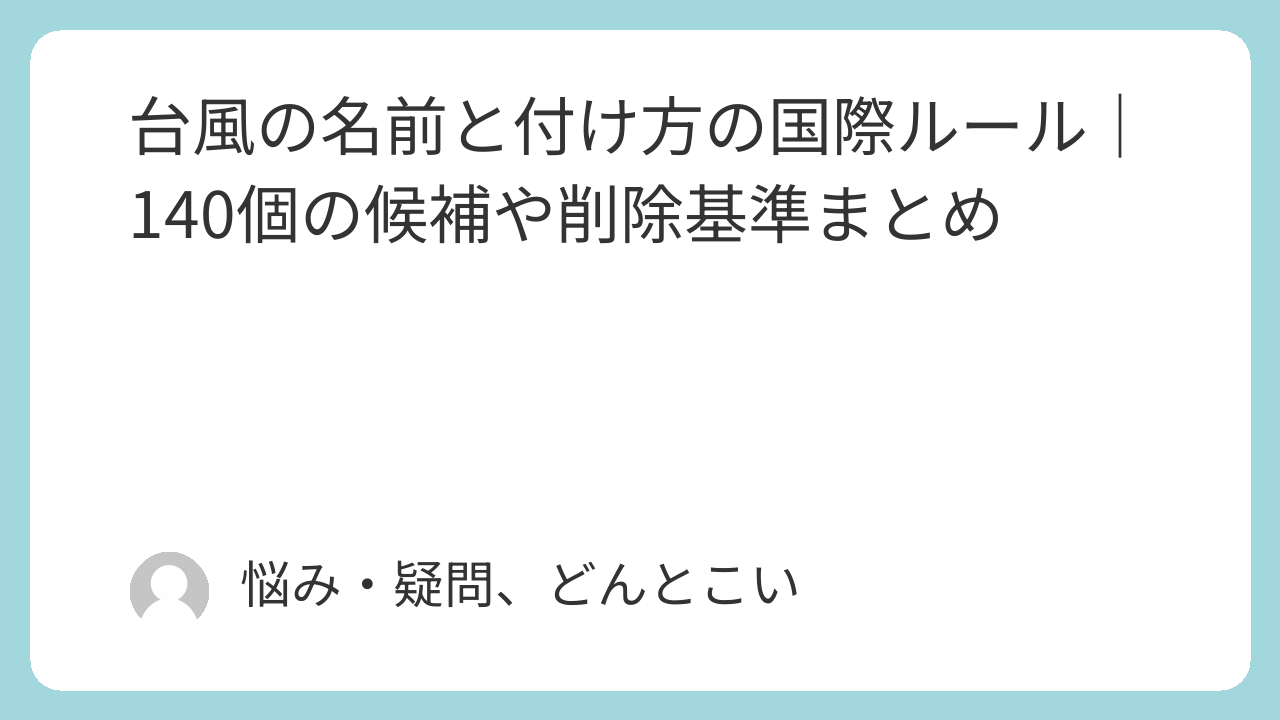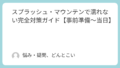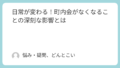台風は「台風5号」のように番号で呼ばれることが多いですが、実は国際的なルールに基づき名前が付けられています。
加盟国が提案した140個の候補を順番に使い、文化や自然、動植物など多様な由来が反映されています。
中には一度きりで削除される名前もあり、その背景には国際的な配慮や混乱回避の目的があります。

本記事では、台風の名前の付け方や由来、削除基準までを一般論として整理しました。
さらに、ハリケーンやサイクロンとの違い、台風接近時の安全対策や情報の入手方法についてもわかりやすくまとめています。
仕組みを知っておくことでニュースや天気予報の理解が深まり、落ち着いた判断の一助になります。
家族や知人との情報共有にも役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
台風の名前はどう決まる?国際ルールと命名の流れ
台風の名前は単なる数字の羅列ではなく、国際的なルールで決められています。
どの国や地域がどのように関わっているのかを知ると、名前の背景や意味がより理解しやすくなります。
まずは、その決定方法と流れから見ていきましょう。
台風の名前を決める組織「台風委員会」とは
台風の名前は、アジアやオセアニアの国や地域が加盟する台風委員会(Typhoon Committee)によって管理されています。
この委員会は世界気象機関(WMO)と国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)の共同運営で、加盟国が提案した名前をリスト化しています。
加盟国は現在14か国・地域あり、日本、中国、韓国、フィリピン、タイなどが含まれます。
それぞれが自然、動植物、文化、歴史などに由来する名前を10個ずつ提案し、合計140個のリストが作られます。
命名の流れと名前が使われる順番
台風の名前は、発生順にこのリストから順番に使用されます。

台風が発生すると、気象機関が該当する名前を選び、その後の公式発表やニュースで用いられます。
一巡すると、再び最初の名前から使われますが、重大な被害をもたらした場合などはその名前が永久に使用停止となり、新しい名前に置き換えられます。
| 加盟国・地域 | 名前の由来の傾向 |
|---|---|
| 日本 | 星座や自然現象(例:テンビン、カジキ) |
| 中国 | 動植物や伝説上の生き物(例:ムーラン、ハグピット) |
| フィリピン | 動物や植物、文化的名称 |
| タイ | 花や神話の名前 |
| 韓国 | 自然現象や伝統的な言葉 |
このように、台風の名前は単なる記号ではなく、各国の文化や自然環境が反映されたリストになっています。
知っておくと、台風名に込められた背景も見えてきます。
台風の名前候補140個一覧|意味や由来もあわせて紹介
140個の台風名は、加盟国や地域が提案した候補から構成されています。それぞれに文化や自然、動植物などの由来があり、世界各地の特色が表れています。
ここでは、日本が提案している台風名も含めて、その意味を見ていきます。
名前の由来は各国の文化や自然現象から
台風の名前は、台風委員会に加盟する14の国や地域がそれぞれ10個ずつ提案したものです。
これらは文化・自然・動植物・歴史など、多様なテーマから選ばれています。

例えば、日本は星座や魚の名前、中国は伝説や動物、タイは花や神話など、各国らしい特徴が見られます。
この背景を知ることで、台風の名前が単なる記号ではないことが分かります。
日本が提案している台風名とその意味
日本が提案した10個の台風名は、海や空、自然にまつわる言葉が中心です。
それぞれに由来や意味があり、災害報道で名前を耳にしたときに少し親しみを持てるかもしれません。
| 台風名 | 由来・意味 |
|---|---|
| テンビン | 星座の「天秤座」 |
| ヤギ | 星座の「やぎ座」 |
| ウサギ | 星座の「うさぎ座」 |
| カジキ | 海に生息する魚のカジキ |
| カンムリ | 鳥の名前(冠を持つ鳥) |
| クジラ | 大型の海洋生物のくじら |
| コグマ | 星座の「こぐま座」 |
| コンパス | 航海や方向を示す道具 |
| トカゲ | 星座の「とかげ座」 |
| ワシ | 星座の「わし座」 |
140個すべてを一覧化すると非常に長くなるため、ここでは日本提案分を中心に紹介しました。
他国の台風名にも、地域の自然や動物、歴史上の人物など、多彩な由来があります。
興味がある方は台風委員会の公式リストを確認すると、世界各地の文化的背景を感じられるでしょう。
一度きりで消える台風名とは?過去の事例と名前削除の条件
一度きりで使われなくなる台風名があることをご存じでしょうか。
これは国際的な配慮や混乱回避のための措置として行われます。その条件や背景を一般論として確認してみましょう。
名前が削除される国際的な基準
台風の名前は、基本的にリストを順番に繰り返して使用しますが、重大な被害や混乱をもたらした台風の名前は永久に使用されません。
これは同じ名前を再び使うことで、過去の被害を想起させたり、混乱を招いたりすることを避けるためです。
この措置は、台風委員会の会議で加盟国の合意により決定されます。
名前が削除された場合は、提案国が新しい名前を提出し、承認後にリストへ追加されます。
削除された台風名の一般的な背景
名前削除の判断は、被害の規模や影響の広がり、国際的な認知度など複数の要因を踏まえて行われます。
下記は一般的な例です。
| 削除理由 | 概要 |
|---|---|
| 甚大な被害 | 被害状況が広範囲かつ深刻で、国際的なニュースとなった場合 |
| 社会的影響 | 復旧や社会生活に長期間影響を与えた場合 |
| 国際的な混乱回避 | 同じ名前を再使用すると、過去の台風と混同されるおそれがある場合 |
このように、名前削除は単なる慣習ではなく、国際的な配慮のもとで決定されます。
知っておくと、ニュースで「この台風名は今回で使われなくなる」という報道があった際、その背景を理解しやすくなります。
台風の名前とハリケーン・サイクロンの違い
台風と似た現象に、ハリケーンやサイクロンがあります。
これらは呼び方や発生する海域が異なり、命名方法も地域ごとにルールがあります。違いを整理しておくことで、ニュースや天気予報をより正確に理解できます。
世界の熱帯低気圧の呼び方と分類
熱帯低気圧は世界中の海域で発生しますが、発生する場所によって呼び方が異なります。
「台風(Typhoon)」は北西太平洋で発生した強い熱帯低気圧の呼称です。
一方、「ハリケーン(Hurricane)」は北大西洋や東太平洋で発生、「サイクロン(Cyclone)」はインド洋や南太平洋で発生した場合に使われます。
| 呼び方 | 発生海域 | 主な地域 |
|---|---|---|
| 台風(Typhoon) | 北西太平洋 | 日本、フィリピン、中国、韓国など |
| ハリケーン(Hurricane) | 北大西洋・東太平洋 | アメリカ、カリブ海諸国、メキシコなど |
| サイクロン(Cyclone) | インド洋・南太平洋 | インド、バングラデシュ、オーストラリアなど |
台風だけが持つ特徴とは
台風は、特に北西太平洋で発生するため、日本や東アジアの天候に大きな影響を与えます。
名称の付け方は台風委員会のルールに基づき、加盟国が提案した名前を順番に使用します。
ハリケーンやサイクロンも国際機関による命名ルールがありますが、地域ごとに候補リストや提案国が異なります。

このため、似た規模や性質を持つ現象でも、地域によって異なる呼称や命名方法が採用されているのです。
台風接近時の安全対策|外出を避けるべき理由と備え方
台風接近時は、風や雨の影響による危険が高まります。外出を控えることが推奨される理由や、自宅でできる備えについて知っておくと安心です。
ここでは、一般的な安全対策を整理します。
強風・豪雨による二次被害を防ぐための準備
台風接近時は、強風や豪雨によって飛来物や浸水などの二次被害が発生する可能性があります。
そのため、不要不急の外出を避けることが安全確保の第一歩です。
自宅では、窓や雨戸の施錠確認、ベランダや庭の飛ばされやすい物の室内移動など、基本的な備えを行いましょう。
また、停電や断水に備えて懐中電灯や飲料水、非常食を準備しておくと安心です。
自宅でできる安全確保の工夫
台風の影響が強まる前に、家族や同居者と連絡方法や避難経路を確認しておくことも重要です。
万一の避難に備え、必要な持ち物(身分証明書、携帯電話、充電器など)をひとまとめにしておくと、慌てずに行動できます。

情報はテレビやラジオ、気象庁の公式サイトなど信頼できる情報源から入手しましょう。
SNSや非公式情報は誤解を招く可能性があるため、事実確認が取れた情報を優先して行動することが大切です。
台風情報の正しい入手方法とチェックポイント
台風情報は刻々と変化するため、正確な情報源からの確認が重要です。
公式発表とそれ以外の情報の使い分けを知っておくことで、落ち着いた行動が取りやすくなります。
信頼できる入手先と注意点を見ていきましょう。
信頼できる公式情報源(気象庁・自治体発表)
台風の進路や影響は刻々と変化するため、正確で信頼できる情報源からの確認が欠かせません。

日本国内で最も信頼性が高いのは、気象庁の公式発表や自治体の防災情報です。
気象庁のサイトでは、台風の現在地や予想進路、雨や風の強さなどを地図や図で確認できます。
また、自治体の防災メールや公式アプリを登録しておくと、避難情報などの重要なお知らせを迅速に受け取れます。
| 情報源 | 特徴 |
|---|---|
| 気象庁公式サイト | 台風の進路、勢力、雨量予測を地図と数値で確認可能 |
| 自治体の防災情報 | 避難所開設情報や避難指示など地域密着の発表 |
| 防災アプリ(NHKニュース防災など) | 速報性が高く、スマートフォンから手軽に閲覧可能 |
SNSや非公式情報の利用時の注意点
SNSは速報性が高い一方で、誤った情報や不確かな情報が含まれる場合があります。
画像や動画、コメントだけで判断せず、必ず公式情報と照らし合わせて確認しましょう。
特に避難や安全に関わる判断は、気象庁や自治体の発表を優先してください。
このように情報源を使い分けることで、落ち着いて正しい行動が取りやすくなります。
まとめ|台風の名前ルールを知って安全意識を高めよう
ここまで台風の名前に関する仕組みや安全に関する情報を整理してきました。
最後に、今回の内容を振り返り、防災意識を高めるためのポイントをまとめます。
台風の命名ルールを知るメリット
台風の名前は、加盟国が提案した候補を国際的なルールに沿って順番に使う仕組みで、背景には各国の文化や自然が反映されています。
このルールを知っておくと、ニュースで名前を聞いたときにその由来や意味を理解しやすくなります。
また、一度で削除される名前の存在を知ることで、報道の背景にも関心を持つきっかけになります。
日常生活での防災意識向上につなげる
台風は日本にとって身近な自然現象であり、影響は季節を問わず発生する可能性があります。

名前のルールや情報の入手方法を把握しておくことで、平時から安全意識を高めることができます。
実際の行動判断や避難は、必ず最新の公式発表を優先してください。
知識はあくまでも準備や心構えの一助として活用し、状況に応じて柔軟に対応することが大切です。
本記事が、台風に関する理解を深め、身近な人と共有しながら備えを見直すきっかけになれば幸いです。