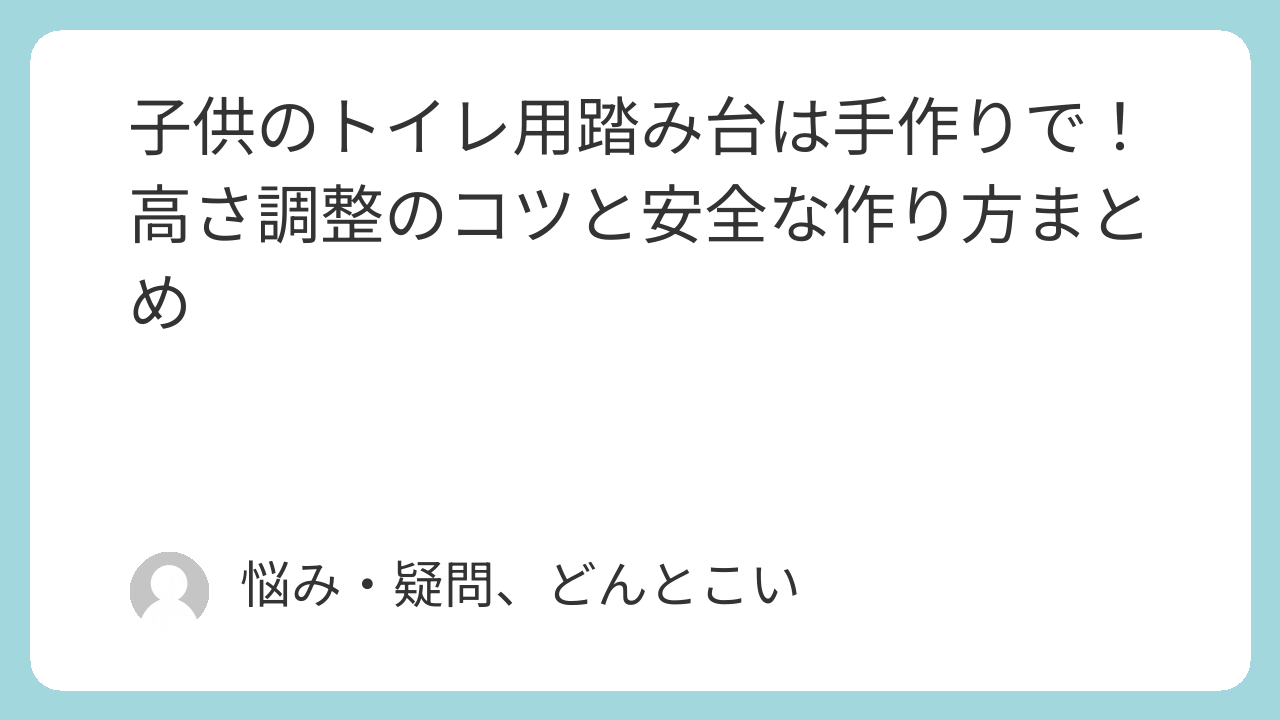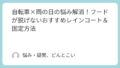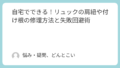子供のトイレトレーニングで「足が届かない」「怖がってしまう」そういう悩みはよく聞かれます。
しかし踏み台があれば足元が安定して安心感が生まれ、排泄もスムーズに進みやすくなります。
でも市販のものでは高さが合わなかったり、デザインが気に入らないことも。

そこで今回は、トイレ用踏み台の役割や高さ調整のコツ、さらに身近な材料でできる手作りアイデアまでたっぷりご紹介します。
忙しいママでもすぐに実践できる内容です!
トイレ踏み台の必要性と種類
トイレ踏み台の役割とは?
子供がトイレを使うとき、足が床につかないと不安定になってしまい、踏ん張る力も入りにくくなります。
特に初めてのトイレトレーニング中は、安心感を持たせることがとても大切です。そんなときに活躍するのが「トイレ用の踏み台」です。
踏み台があることで、足がしっかりと地面についているような感覚を得られ、自然と体勢も安定。
踏ん張る力が入りやすくなるので、排泄もしやすくなります。
トイレが怖くなくなることで、子供の自立もぐんと進みやすくなりますよ。

また、便座に座るときのよじ登りもサポートしてくれるので、親の負担も少し軽くなります。
市販の踏み台には、高さが調整できるタイプや、便座の形にフィットするデザインなど、いろいろな種類があります。使う場所や子供の体格に合わせて選ぶことが大切です。
子供に必要な踏み台の高さ
踏み台の高さは、子供の年齢や身長によって最適なものが異なりますが、基本的には「足裏全体がしっかり踏み台に乗る高さ」が目安になります。
トイレに座ったとき、足が浮いてしまうと踏ん張りにくくなり、排泄がスムーズにできないことも。逆に踏み台が高すぎると座りにくくなってしまうので、注意が必要です。

だいたいの目安としては、2~3歳の子なら15cm前後、4~5歳なら20cm前後が使いやすい高さとされています。
ただし、これはあくまで目安なので、実際にトイレに座らせてみて足が自然に置ける高さに調整してあげるのがベストです。
子供の成長に合わせて高さを変えられる踏み台や、手作りで調整しやすい設計にするのもおすすめです。
手作り踏み台のメリット
自作する際の注意点
踏み台を手作りする魅力は、コストを抑えつつ、子供の成長やトイレ環境に合わせて柔軟に対応できるところです。
ただし、安全性には十分注意が必要です。
まず第一に「ぐらつかないこと」がとても重要です。
材料の強度や組み立て方によっては、使っている途中で崩れる恐れもあるため、安定感をしっかり確認しましょう。
また、角がとがっていないか、滑り止めが付いているかなどもチェックポイントです。

作った後は、子供に実際に使わせてみて、安全に乗り降りできるかどうかを必ず確認するようにしてください。
牛乳パックを使った簡単な作り方
牛乳パックは軽くて扱いやすく、家庭にあるものを使って踏み台が作れるため、手作りの中でも特に人気です。
目安としては、1リットルサイズのパックを12本程度使います。
パックは中を洗ってしっかり乾かし、口を閉じてからテープでしっかり固定します。それを2列6本ずつに並べ、段ボールや布で全体を包むと、見た目もきれいで強度もアップ。
最後に、裏側に滑り止めシートを貼っておけば、さらに安心して使えます。
段ボールを活用した踏み台
段ボールも、家にあるもので手軽に作れる素材のひとつです。
コツは「重ねて強度を出す」こと。
1枚では強度が足りないので、何枚も貼り合わせて積層構造にすると、しっかりした踏み台に仕上がります。

段ボールの中に空間を作るとつぶれやすくなるため、内部にも詰め物をするか、柱状に仕切りを設けると安定感が出ます。
見た目を整えるためには、布やリメイクシートで全体を覆うのもおすすめです。軽いので、子供でも移動させやすいのがメリットです。
木製踏み台の設計と作り方
木材を使えば、しっかりとした踏み台を作ることができます。
長く使いたい場合や、インテリアになじませたいときにぴったりの素材です。
ホームセンターでカット済みの板を使えば、DIY初心者でも比較的スムーズに作れます。
基本的には天板(踏む部分)と側板をL字型に組み、補強の板を入れてビスで固定。角はやすりで丸くしておくと安心です。

好みに合わせて、ペンキやニスで色を塗ったり、名前を入れてアレンジするのも楽しめます。
100均アイテムを使った踏み台
手軽に材料をそろえたいなら、100均のアイテムを活用する方法もあります。
すのこや収納ボックス、ジョイントマットなどを使えば、組み合わせ次第で意外としっかりした踏み台が完成します。
すのこは複数枚をボンドやネジで固定すると安定感が出ますし、収納ボックスの中に重しを入れて使うと実用性もアップ。
耐荷重などはアイテムごとに違うので、商品パッケージをよく確認して、用途に合ったものを選ぶようにしてください。
踏み台の高さ調節方法
必要な高さの測り方
踏み台を用意する際にまず大事なのが「必要な高さをどう測るか」です。
子供がトイレに座ったとき、足の裏がしっかりと踏み台に乗る状態が理想的です。
そのため、実際に補助便座に座らせた状態で、足が自然に降りる位置までの距離を測ってあげましょう。

メジャーで床から足の裏までの高さを測ればOK。数センチの余裕をもたせることで、踏みやすく安定感も出やすくなります。
また、足首が90度に曲がって足裏全体が台に接しているかも確認してみてください。これがスムーズな排泄姿勢につながります。
子供の成長に合わせた高さの調整
子供は成長が早く、数か月で体格が大きく変わることもあるため、踏み台もできれば高さを調整できる設計が理想的です。
たとえば、重ねられるブロック式の踏み台や、高さを段階で変えられる木製の踏み台などを使えば、成長に合わせて無理なく調整できます。
手作りの場合は、数センチ単位で高さを変えられるように設計しておくと便利です。
ネジで高さを固定する仕組みにしたり、板を差し替えて高さを変える構造にすると長く使えます。
定期的に座らせてチェックし、足が浮いていたり逆に台が高すぎて膝が不自然に上がっていないかを確認するのがポイントです。
トイレトレーニングと踏み台の関係
踏み台でトイレトレーニングを楽にする方法
トイレトレーニングは、子供にとってもママにとっても大きなチャレンジ。
でも、ちょっとした工夫でグッとスムーズになるんです。その一つが「踏み台の活用」です。
足元が安定しているだけで、子供は安心して便座に座ることができ、排泄への不安感も軽減されます。
足がしっかりついていることで、自然と踏ん張る力も入りやすく、排泄がスムーズにいきやすくなるんです。

また、自分で便座に座ったり降りたりできるようになると、トイレに対する自信も芽生えて「自分でやりたい!」という意欲にもつながります。
毎日の習慣の中で「安心して使える踏み台」があることで、子供もトイレを怖がらず、自然とトレーニングが進んでいきます。
おすすめの補助便座と踏み台
踏み台と一緒に使いたいのが「補助便座」。
大人用のトイレにそのまま座るのは不安定ですが、補助便座をセットすればサイズもフィットして安心感がアップします。
補助便座は、持ち手付きやクッション素材、ステップ一体型などさまざまなタイプがあります。
選ぶポイントは「しっかり固定できてずれにくいこと」。子供が動いても安定しているかどうかを確認しましょう。
踏み台との相性も大事なので、できれば補助便座とセットで使えるシリーズや、踏み台の高さに合わせて選ぶのがおすすめです。
特にワンタッチで設置できるものや、収納しやすいタイプは忙しい毎日にぴったり。

子供の好みに合ったカラーやキャラクター付きのものを選ぶと、トイレに行くのが楽しくなるかもしれません。
踏み台のデザインとインテリア
踏み台をおしゃれにするアイデア
機能性だけでなく、見た目にもこだわりたいのが今どきの子育てアイテム。
踏み台も「おしゃれ」に仕上げることで、トイレの雰囲気が明るくなり、子供も使いたくなるきっかけになります。
例えば、木製の踏み台ならナチュラルカラーで統一したり、北欧風のデザインにペイントするのも人気。
シンプルなデザインにステッカーを貼って子供らしさをプラスするのも素敵です。
布やリメイクシートを使えば、手軽に雰囲気を変えることも可能。季節ごとに柄を変えて、模様替え感覚で楽しむのもおすすめです。
子供部屋に合うデザイン選び
踏み台はトイレだけでなく、子供部屋で使うこともあります。
その場合、部屋の雰囲気に合ったデザインにすると、インテリアとしても自然に馴染みます。

例えば、家具と同じ色味でまとめたり、好きなキャラクターのモチーフを取り入れることで、子供が自分の空間として愛着を持ちやすくなります。
また、子供部屋では安全面も重視したいので、角が丸く加工されているものや、軽くても倒れにくい設計を選ぶと安心です。持ち運びしやすい取っ手付きも便利ですよ。
踏み台の収納方法と工夫
使わないときに邪魔にならないように、収納しやすい工夫も大切なポイントです。
コンパクトに折りたためるタイプや、重ねて収納できる構造の踏み台は、省スペースで使い勝手が良好。
また、トイレや洗面所のちょっとしたすき間に入るサイズにしておくと、出し入れもスムーズです。
フック付きで壁に掛けられるデザインも、スペースを有効活用できます。
収納そのものがインテリアとして映えるように、色や形にもこだわって選んでみると、生活感を抑えつつ実用性もキープできます。
踏み台の活用法
日常生活での踏み台の使い方
踏み台はトイレだけでなく、日常のさまざまな場面で活躍する便利アイテムです。
たとえば、洗面所での手洗いや歯磨きのときに使えば、子供が自分で蛇口に手を届かせやすくなります。

キッチンでお手伝いをしたいときにも、踏み台があれば作業台の高さに手が届きやすくなり、「やってみたい!」という気持ちをサポートできます。
ほかにも、靴を履くときや、ベッドに登るときなど、ちょっとした高さが必要なシーンで重宝します。
トイレ以外での踏み台の利用
トイレ以外にも踏み台は使い道がたくさんあります。
例えば、玄関で靴を履くとき、リビングで本棚の上段に手が届かないとき、あるいはお絵かきやおやつの時間にちょっと座る椅子代わりとしても活躍します。
また、子供自身が「自分の場所」として使えるようになると、持ち運んで自発的に使うようになることもあります。
こうした習慣が、自立心を育てるきっかけにもつながりますよ。
軽くて持ち運びしやすい踏み台なら、家の中で自由に使えるので、一つあると本当に便利です。
子供が喜ぶ踏み台の工夫
踏み台を「楽しいアイテム」にすることで、子供の行動にも良い変化が生まれます。
たとえば、好きなキャラクターのシールを貼ったり、名前や模様を入れて「自分専用」にするだけでも、喜んで使ってくれることが増えます。
踏み台の色や形を可愛らしくアレンジするのもおすすめ。

星や動物モチーフ、カラフルなデザインなど、見た目にワクワクする工夫があると、子供のテンションも上がりやすくなります。
また、踏み台を通して「自分でできた!」という達成感を得られるように、使いやすさにも気を配ってあげると、自発的な行動がどんどん増えていきますよ。
まとめ
* 踏み台はトイレでの安定感や安心感をサポート
* 高さは足裏がしっかりつく位置が目安
* 牛乳パックや段ボールなどで簡単に手作りできる
* 成長に合わせて高さ調整できる構造が理想
* デザインや収納にもこだわれば、より快適に使える
* トイレ以外の場面でも踏み台は大活躍!

子供が「自分でできた!」と笑顔になれるアイテムづくり、ぜひ楽しみながらチャレンジしてみてくださいね。