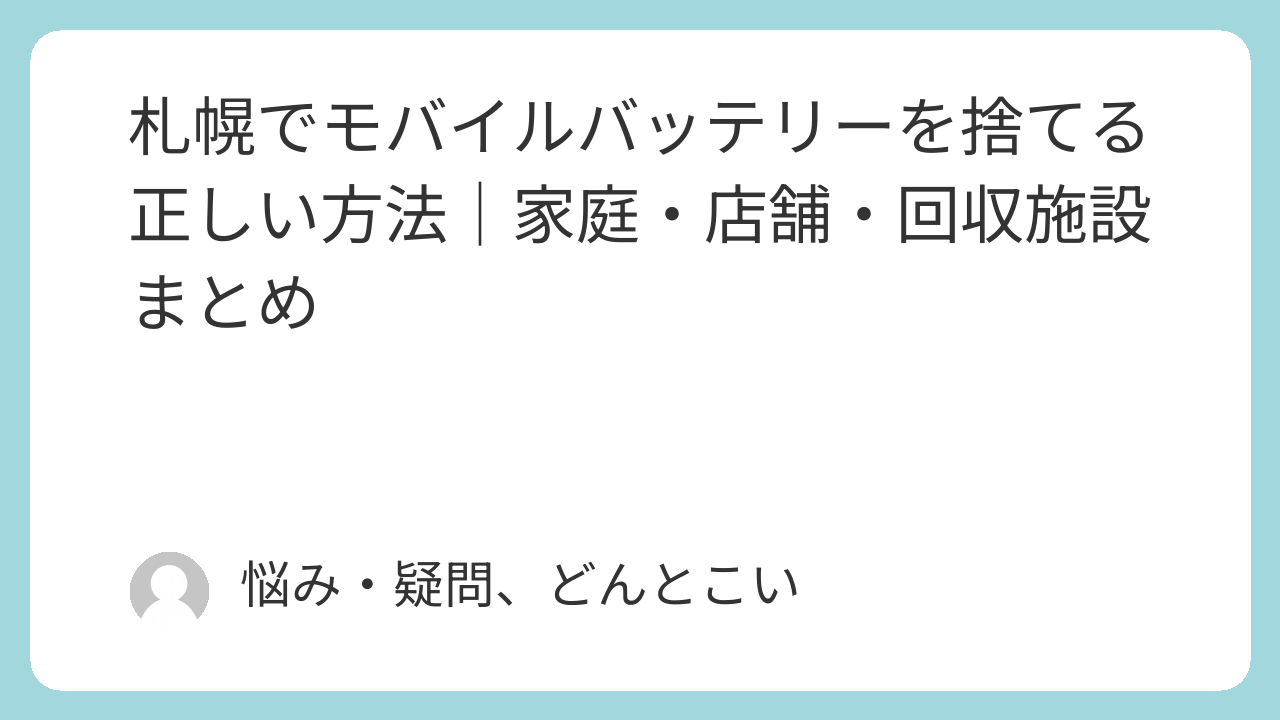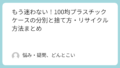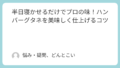スマートフォンや電子機器の普及により、モバイルバッテリーは私たちの生活に欠かせない存在となりました。
しかし、使用後の処分方法に迷う方も多いのではないでしょうか?
特に札幌市では、バッテリーの種類や状態によって回収方法が異なり、間違った処分は環境や安全面に悪影響を及ぼすことも。

そこで本記事では、札幌市でのモバイルバッテリーやコイン電池の正しい捨て方について、自治体のルールや回収ボックスの活用法、リユースの視点も交えてわかりやすく解説します。
家庭や店舗、公共施設など、それぞれのシーンに応じた安全かつスムーズな処分方法を知って、無駄なく賢くバッテリーを手放しましょう。
札幌におけるモバイルバッテリーの捨て方
モバイルバッテリーとは?
モバイルバッテリーとは、スマートフォンやタブレットなどの電子機器を外出先でも充電できる持ち運び可能なバッテリーのことです。
内蔵されているリチウムイオン電池は繰り返し使用が可能で便利ですが、寿命を迎えると適切な方法で処分する必要があります。
特にモバイルバッテリーは発火や発煙のリスクがあるため、家庭ゴミとしては捨てられません。
捨て方の基本知識
モバイルバッテリーの正しい捨て方としては、リサイクルを前提とした回収が基本です。
多くの自治体では「小型家電リサイクル法」に基づき、回収ボックスを設置しています。
ただし、地域によって対応方法が異なるため、住んでいる自治体のルールを確認することが重要です。
また、電池が取り外せない一体型タイプのバッテリーは特に注意が必要で、専門の処理が必要となるケースもあります。
札幌市の回収方法
札幌市では、モバイルバッテリーを含む小型電子機器を回収する専用のボックスが市内各所に設置されています。
主に区役所、公共施設、家電量販店などに設置されており、「使用済小型家電回収ボックス」として利用可能です。

札幌市のホームページでは、回収対象品目や設置場所の詳細が掲載されているので、事前に確認してから持ち込むと安心です。
また、電池が膨張している、破損しているといった状態のバッテリーは、安全上の理由から持ち込みを断られる場合があるため、事前に施設へ問い合わせることが推奨されます。
リチウムイオン電池の特性と注意点
リチウムイオン電池の特性
リチウムイオン電池は、高エネルギー密度で軽量、そして繰り返し充電可能という特性を持ちます。
これによりスマートフォンやノートパソコン、モバイルバッテリーなどに広く採用されています。
しかしながら、過充電や強い衝撃、高温環境などによって内部で化学反応が進み、異常発熱や膨張、最悪の場合は発火を引き起こすことがあります。
膨張した電池の取扱い
リチウムイオン電池が膨張した場合は、決して自宅で無理に処理せず、速やかに専門機関へ相談しましょう。
膨張は内部のガス発生などが原因で、圧力が高まった状態となっており、破裂や発火の危険性が高くなっています。
札幌市の回収ボックスでは、膨張した電池は受け付けていない場合が多いため、民間のリサイクル業者や家電量販店の専門窓口への持ち込みが安全です。
発火のリスクと対策
リチウムイオン電池の発火リスクを避けるためには、普段からの適切な使用と保管が重要です。
充電中は可燃物の近くを避け、目の届く場所で行うことが推奨されます。
また、衝撃を与えないよう丁寧に取り扱い、高温多湿の場所には保管しないようにしましょう。
不要になった場合も、破損や劣化が進む前に適切な方法で早めに処分することが、安全と環境保全の観点からも大切です。
札幌での回収ボックスの利用法
利用方法と注意事項
回収ボックスを利用する際は、対象となる品目かどうかを事前に確認することが重要です。
投入する際は、電池部分が露出しないようにテープで絶縁処理を行うなど、安全対策を講じてください。
また、回収ボックスは無人で運営されていることが多いため、壊れた電池や膨張・発火の恐れがあるものは投入せず、専門窓口へ相談するようにしましょう。
投入時には、他のごみや液体を混入させないようご注意ください。
回収可能な品目
札幌市の回収ボックスで受け付けている主な品目は、モバイルバッテリー、携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラ、ゲーム機、USBメモリ、電卓、電子辞書などの小型電子機器です。
ただし、製品のサイズや種類によっては対象外となる場合もあるため、詳細は札幌市公式サイトや設置施設の案内を確認してください。
また、コイン電池や充電式電池単体などは、別途指定された回収方法に従う必要があります。
家電製品との違い
モバイルバッテリーと家電製品の捨て方の違い
モバイルバッテリーと一般的な家電製品では、処分方法が異なる点に注意が必要です。
家電リサイクル法の対象であるテレビや冷蔵庫などの大型家電は、指定された方法で収集運搬され、専用施設で処理されます。
一方で、モバイルバッテリーは小型家電リサイクル法の対象として回収されることが多く、専用の回収ボックスなどを通じて市民が手軽に処分できる体制が整っています。
つまり、同じ電気製品であっても法律や処分ルートが異なるため、廃棄前には必ず確認が必要です。
混ぜてはいけない廃棄物
家電製品やモバイルバッテリーの処分時には、他の種類の廃棄物と混ぜて出さないことが重要です。
特に電池やバッテリー類は発火や有害物質の漏出の危険があるため、通常の可燃ごみ・不燃ごみと一緒に出すことはできません。

また、精密機器内に含まれるレアメタルなどの有効資源を回収するためにも、分別回収は欠かせません。
札幌市では、各品目に応じた明確な分別ルールが設けられているため、公式情報を確認したうえで、正しい処分を心がけましょう。
札幌市のリサイクルシステム
リサイクルマークの意味
製品に表示されているリサイクルマークは、その製品が回収対象であることや、再資源化が可能であることを示す目印です。
たとえば、小型家電リサイクルの対象であることを示すマークや、リチウムイオン電池に見られる特定のリサイクルロゴなどがあります。
これらのマークを確認することで、使用後に適切な回収ルートへと回す判断がしやすくなります。
家電リサイクル法の概要
家電リサイクル法(正式名称:特定家庭用機器再商品化法)は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンといった家電製品を対象に、使用済製品の再資源化を義務付けた法律です。
この法律により、消費者はリサイクル料金を支払い、指定された方法で廃棄物を引き渡す必要があります。
札幌市でもこの法律に基づき、指定業者や販売店を通じて適正なリサイクルが行われていて、市民が正しい手順で処分できるよう啓発活動も積極的に行われています。
店舗の回収協力について
JBRC回収協力店一覧
JBRC(一般社団法人JBRC)は、充電式電池のリサイクルを促進する団体で、全国の協力店で使用済み電池の回収を行っています。
札幌市内でも、家電量販店、ホームセンター、ドラッグストアなどがJBRCの回収協力店として登録されていて、公式サイトでは店舗一覧が公開されています。
お住まいの近くの協力店舗を検索しやすく、利便性が高いのが特徴です。
利用できる店舗の特徴
JBRC回収協力店の多くは、日常的に利用する店舗が多いため、買い物ついでにバッテリーを持ち込めるという利点があります。

また、店頭には専用の回収ボックスが設置されており、営業時間内であればいつでも自由に利用可能です。
対象となるのは主に充電式電池や一部の小型電子機器で、家庭で使用するモバイルバッテリーなども回収対象に含まれることがあります。
店舗での回収の流れ
回収の際は、まず対象製品であるかどうかを確認した上で、電極部分に絶縁処理(テープでの保護など)を施します。
回収ボックスが設置されている店舗に到着したら、スタッフに声をかける必要はなく、そのままボックスに投入するだけで完了です。
ただし、破損していたり膨張しているバッテリーについては、店頭での回収を断られる場合もあるため、事前に店舗へ確認することが推奨されます。
家庭での適切なバッテリー処分法
家庭での分別のポイント
家庭でモバイルバッテリーや充電式電池を処分する際は、まずその製品がどの回収ルートに適しているかを確認することが重要です。
リチウムイオン電池を内蔵する製品は、通常の可燃ごみや不燃ごみに混ぜて出してはいけません。
自治体の回収ルールや、製品に記載されているリサイクルマークなどを参考にし、指定された回収ボックスや協力店へ持ち込むようにしましょう。
包装や容器のリサイクル方法
バッテリーや電子機器には、プラスチックや紙などの包装材が使われていることが多く、それらも適切に分別する必要があります。
札幌市では、プラスチック容器包装と紙製容器包装を分けて収集しており、それぞれのリサイクルマークを確認してから分別するようにしましょう。
バッテリーの本体とは別に処理することで、リサイクルの効率も高まります。
処分時の注意事項
バッテリーを処分する際は、電極部分に必ず絶縁処理を施しましょう。
金属と接触した場合、ショートして発火する危険があります。
また、破損していたり膨張している電池は、決して無理に処分せず、専門機関やリサイクル受付店舗に相談するのが安全です。
自治体の収集日や対象品目を確認し、ルールに沿った形で処分することが、家庭から始める安全で持続可能なリサイクルの第一歩となります。
モバイルバッテリーのリユースと再利用
リユースのメリット
モバイルバッテリーのリユースは、資源の有効活用や廃棄物削減に貢献する方法のひとつです。

バッテリー自体がまだ十分に使用可能であれば、再利用や譲渡によって製品寿命を延ばすことができます。
これにより、新たな製品を製造するための資源やエネルギーの消費を抑えられ、環境保全にもつながります。
特に頻繁に充電をしない人なら、少し古いバッテリーでも十分活用できるケースが多いです。
もったいない精神と環境
日本には昔から「もったいない」という精神が根付いており、リユースや再利用の考え方とも深く結びついています。
まだ使えるものを捨てずに活用する姿勢は、環境への負荷を減らし、持続可能な社会づくりに貢献します。
モバイルバッテリーも、正しく点検・管理することで、思った以上に長く使えることがあり、「もったいない」の精神を実践する一例として注目されています。
再利用できる製品例
再利用が可能な製品としては、外装に傷があるものの機能的には問題ないモバイルバッテリーや、容量がやや低下したもののサブ機として使える製品などがあります。
また、家族や友人とのシェアや、フリマアプリ・リユースショップなどを通じた再流通も有効です。
ただし、安全性を確保するためにも、過度に劣化した製品や異常を感じるものはリユースを避け、適切に処分する判断も大切です。
回収施設の情報
札幌の主な回収施設
札幌市では、モバイルバッテリーや小型電子機器を安全に回収するために、複数の公的・民間施設が対応しています。
代表的な施設としては、各区役所内に設けられているリサイクルステーション、市内の清掃工場、エコプラザ、または環境事業公社などが挙げられます。
これらの施設は、市民が安心して持ち込める体制が整っており、分別や処分方法の相談も可能です。
施設の利用時間とアクセス
各回収施設の利用時間は、平日の日中(8:45~17:15)が中心ですが、施設によっては土曜や祝日に対応しているところもあります。
アクセスについては、公共交通機関で行ける立地にある施設が多く、徒歩や自転車でも訪れやすいよう配慮されています。
ただし、施設によっては事前予約が必要な場合や、特定の曜日のみ回収を行っているところもあるため、公式ホームページや電話での事前確認が推奨されます。
地域別の回収情報
札幌市は10区に分かれており、それぞれの区で回収対応や施設情報が異なることがあります。
中央区では市民交流プラザ内のリサイクルスポットが利用しやすく、北区や東区では清掃工場の受付窓口が活用されています。
西区や手稲区では地域のスーパーや区役所などに設置された回収ボックスが便利です。
住んでいる地域に応じた最適な回収方法を知るためには、札幌市公式サイト内の「資源・ごみ分別検索」ページを活用するのが便利です。
まとめ
モバイルバッテリーやコイン電池などの小型電池は、便利である一方、処分方法を誤ると火災や環境汚染の原因になりかねません。
札幌市では、各区の施設や店舗に回収ボックスが整備されていて、リチウムイオン電池の特性を理解したうえで安全に手放すことが求められています。

今後も増え続ける電子機器と上手に付き合うために、今回ご紹介した知識をぜひ日常に取り入れてみてください。